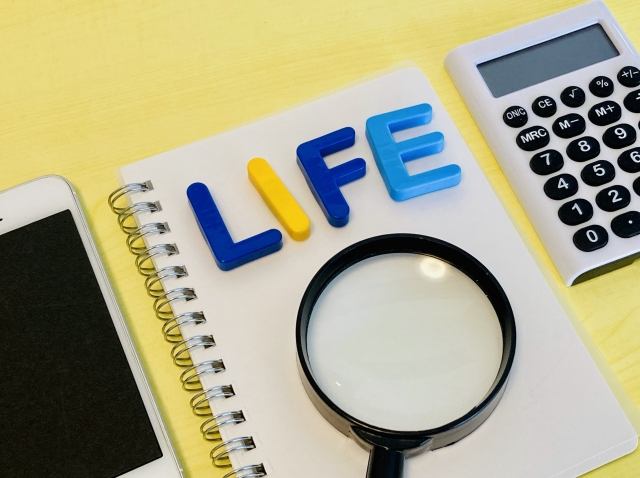
家計管理
はじめに
大学や大学院での学びを支えてくれる奨学金。進学の際には大きな支えとなる一方で、卒業後には返還という現実が始まります。
奨学金を返しながらの生活は、実際どのようなものなのでしょうか。
この記事はあくまで私自身の体験に基づいた内容であり、人によって感じ方や状況はさまざまです。そのうえで、返還生活の印象を振り返ってみたいと思います。
返還総額と返還期間のイメージ
奨学金の返還は、人によって額も期間も異なります。借入額が大きければ返還も長期化し、少なければ比較的早く区切りをつけられます。
返還方式には、毎月一定額を支払う定額返還方式と、収入に応じて返還額が変わる所得連動返還方式があります。いずれにしても、長く続いていく返還を生活の中に組み込んでいく点は共通しています。
また、奨学金貸与・返還シミュレーションを活用すると、借入額や条件を入力するだけで、毎月の返還額や返還総額を確認できます。返還開始前に試してみると、将来の生活設計がぐっと具体的になります。
利率と一括返還の経験
奨学金には「無利子」と「有利子」があり、有利子の場合は返還が長期化するほど利息の負担が増えます。そのため、繰り上げ返還や一括返還を検討する人も少なくありません。
私自身も、有利子の奨学金については修了時に一括返還を選びました。そのときは「利息が増えない安心感」と「返還の義務から解放される安堵感」が大きなメリットに思えました。ただ、振り返ってみると「手元に資金を残しておけば別の活用ができたのでは」という考えも浮かびます。
一括返還が良いかどうかは一概に言えません。利息を抑えられる安心感と、資金を手元に残す安心感。どちらを優先するかは、人それぞれの状況や価値観によって変わるのだと思います。
返還が続く日々の感覚
返還を始めた当初は、給与から自動で引き落とされる金額を毎月確認しながら、「あとどれくらい続くのだろう」と感じることがよくありました。
明細を見るたびに重さを覚え、日本学生支援機構(JASSO)のホームページで返還状況を確認して、残りの回数や残高を見ながら「少しずつ減っている」と受け止めていました。複数の奨学金を借りていたため、それぞれの返還が終わるたびに「やっと一区切りついた」という安堵感もありました。
また、奨学金を借りて学んだ経験があるからこそ、「この学びを無駄にしないようにしたい」という気持ちも生まれました。返還を続けるなかで、借りたおかげで得られたものを活かそうという思いが自然と芽生えていたように思います。
長い道のりでしたが、そうして返還を重ねていくうちに、少しずつゴールが近づいていることを実感できたのは支えになりました。
完了したときの実感
すべての返還が終わったときには、肩の荷が下りたような感覚がありました。
「これで一区切りついた」という安堵感とともに、負債があるのとないのとでは気持ちの軽さが大きく違うのだと実感しました。
返還の義務から解放されたあとの生活では、それまでよりも気持ちに余裕が生まれたように感じます。
奨学金返還生活で感じたこと
10数年にわたって奨学金を返してきた経験から、次のようなことを感じました。
- 長く続く義務感は重さもあったが、その分「やり遂げた達成感」も大きかった
- 返還状況を定期的に確認することで、少しずつ前に進んでいることを実感できた
- 奨学金を借りて学んだからこそ、その学びを活かそうと考えることができた
- 完了したときの安心感は、長く続いた返還生活の終わりを実感させるものだった
まとめ
奨学金を返還しながらの生活は、借入額や利率、返還期間、そして各人の状況によって大きく変わります。
数字そのものは人によって違いますが、共通して言えるのは「返還は長く続く」ということ。その道のりのなかで負担を感じることもありますが、少しずつ減っていく残高を確認しながら進めば、やがて確かな区切りが訪れます。
奨学金を返している方、これから借りる方にとって、この記事が少しでも生活のイメージづくりや気持ちの整理の助けになれば幸いです。
研究者と研究者を目指す方々が、やりたいことをあきらめないでいられることを願って。
