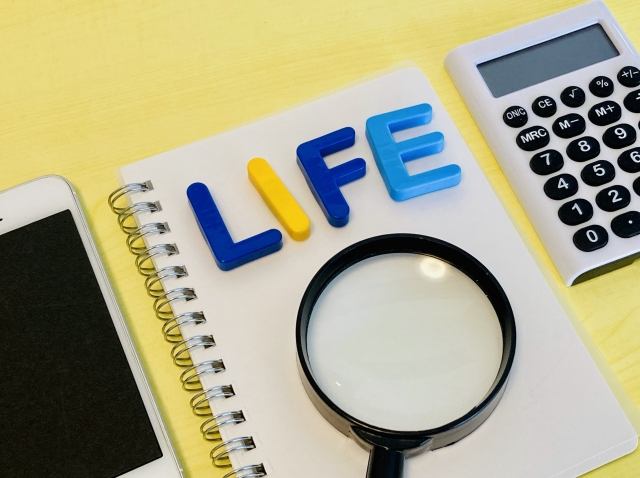
家計管理
「おすすめ」に違和感を抱いたことはありませんか?
「今ならお得です」「一番人気ですよ」
こんな言葉に、思わず心が動いたことはありませんか?
私たちは日々、何かを「すすめられる」立場で生活しています。買い物、保険、習い事、携帯電話の通信プラン、住宅など、提案される機会は少なくありません。
一方で、「本当に私のための提案なのか?」「売る側の都合では?」といったモヤモヤを感じたことがある方もいるでしょう。
その背後にあるのが「利益相反(りえきそうはん)」という状態です。
利益相反とは何か?
たとえば、あるお店のスタッフが「この商品がおすすめですよ」と提案してきたとします。
スタッフは、買い手にとって本当におすすめだと考えて提案したのかもしれません。
一方で、「店舗として売りたい商品である」「販売インセンティブがついている」「在庫を早く処分したい」といった“売る側の事情”があって提案した可能性もあります。
このスタッフが置かれた状態のように、ある立場に立った場合の利益と同じ人が別の立場に立った場合の利益が相反している状態が、利益相反の状態と言えます。
これは特別な状況ではなく、医療現場、教育現場など、さまざまな現場で自然に生じうる状態だと思います。
売る人=悪ではない
ここで大切なのは、「利益相反がある=悪意がある」というわけではない、という点です。
販売やサービスの提供は事業として行われており、売上目標やインセンティブがあるのは自然なことです。
ほとんどの販売員や専門職は、誠実に相手の役に立とうとしながらも、同時に事業の持続可能性を考えています。
だからこそ、「利益が絡む=信用できない」と極端に構えるのではなく、相手の立場と構造を理解しながら、冷静に選べる力が必要なのです。
立場が一致する場合もある
もちろん、売り手と買い手の利益が一致する場面も存在します。
たとえば、
- 成果報酬型のコンサルやトレーナー
- 満足度が次の仕事につながる専門職
- 自分でも使って満足している商品を紹介する販売員
こうした場合、「売る側の成果=買う側の満足」という構造が成立しています。
すべてを疑うのではなく、「この人の提案は、どの立場からなされているのか?」「その立場は自分とどれほどズレているのか?」といった視点をもつことが大切です。
メタ認知が支える冷静な判断
こうした場面で役立つのが、「メタ認知」と呼ばれる概念です。
メタ認知とは、自分の認知(考えや感情)を一歩引いて見つめることと言い換えることができると思います。
たとえば、何かをすすめられたときに、
- 「私は今、熱意に押されて買おうとしているのでは?」
- 「“お得”という言葉に惹かれているだけかも?」
- 「これは本当に自分に必要なものだろうか?」
- 「売る側にメリットがあるだけなのでは?」
と、自分に問い直すことで、感情に流されすぎず冷静に判断することができます。
これは、相手を疑うというよりも、自分を守る方法です。
信じすぎず、疑いすぎず、後悔しない選び方を
人は、信じることで人とつながり、選ぶことで人生をつくっていきます。
信頼しすぎて損をすることもあれば、疑いすぎて大切な機会を逃すこともあります。
だからこそ、「疑いすぎず、信じすぎず」のバランスが重要です。
そのためには、利益相反という構造を知り、相手の立場を想像し、自分の気持ちにも目を向けることが重要なのだと思います。
その上で、「自分にとって、これは納得できる選択か?」と問い直すことが、後悔の少ない判断へと導いてくれると思います。
提案を受けることを怖がらず、かといって流されることもなく、納得して選ぶ。
そんな自分なりの選び方を、日常の中で育てていくのはいかがでしょうか?
今回は、利益相反を理解しながら、疑いすぎず信じすぎず、納得できる選択をするための考え方について書きました。
何らかの参考になれば幸いです。
研究者と研究者を目指す方々が、やりたいことをあきらめないでいられることを願って。
