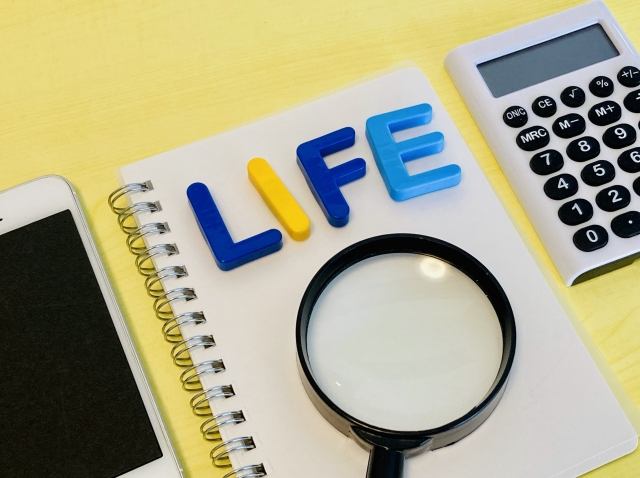
書籍紹介
過去記事まとめ:研究者のライフプランを考えるための書籍
これまで当ブログでは、研究者のキャリアとライフプランについて、多角的な視点から考えるための様々な書籍をご紹介してきました。このまとめ記事では、これまでに紹介した書籍の概要と主な見どころを改めてご紹介します。研究者を目指す方、現役の研究者、そしてアカデミア以外の道も視野に入れている方々にとって、自身の未来を考える上で役立つヒントが見つかれば幸いです。
心理学の多様な進路を考える一冊
『大学で心理学を学びたいと思った時に読む本』は、心理学を学びたい高校生や大学生の進路選択をサポートする一冊です。心理学の幅広い分野や、カウンセラー以外のキャリアパス、海外留学の選択肢など、具体的な未来像を描くための情報が満載です。
「『心理学=心理職』ではなく、『心理学=人間の幸せに貢献する』という視点を持つこと」という言葉が印象的で、心理学が社会の様々な場面で役立つ可能性を示唆しています。
働きながら博士号を目指す社会人への実践的ガイド
『働きながらでも博士号はとれる』は、特に働きながら博士号取得を目指す社会人に向けて書かれた本です。仕事と研究を両立させるための具体的なテクニックや、社会人が直面するであろう苦労への助言が、著者の実体験に基づいて詳細に解説されています。
「一生のうちでなかなか経験できないこの時を、皆さんには是非楽しむ気持ちで臨んでいただきたい」という一節は、多忙な中でも夢を追いかける読者への力強いエールとなるでしょう。
子育てとリスキリングの両立に挑む体験記
『子育てリスキリング奮闘記 休職サラリーマン、二児を抱えて教育系大学院で学ぶ』には、子育て中の社会人が勤務先を休職し、大学院で教育学修士と教員免許を取得した際の貴重な体験談です。家族を抱えながらの学び直しのリアルな心情や、奨学金・授業料免除に関する具体的な情報が赤裸々に綴られています。
著者の「子育てと大学院での勉強の両立は生半可なものではなかったにせよ、そこで学んだ教育学は、学校教育だけではなく、子育てにも大いに役立った」という言葉は、学びが実生活に直結する可能性を示しています。

理工系研究者が知っておくべき「研究以外」のノウハウ
『研究者としてうまくやっていくには 組織の力を研究に活かす』は、理工系研究者を目指す方々に向けて書かれた書籍で、研究活動以外の側面、特に組織の中で研究を進める上でのノウハウに焦点を当てています。研究者としての長期的なライフプランを捉える視点や、研究不正に関する内容も含まれています。
「大学教授が『高等遊民』と言われて自分の好きな研究に没頭できていた時代はとっくに終わりました」という著者の言葉は、現代の研究者に求められる多岐にわたる役割を明確に示唆しています。
文系研究者のキャリアパスを網羅したガイドブック
『文系研究者になる:「研究する人生」を歩むためのガイドブック』は、特に人文系研究者を目指す方にとっての道しるべとなる一冊です。大学院進学から専任研究者となるまでの過程で必要となる考え方や実行すべきことが、細部にわたって解説されています。経済的な問題やキャリアに関する現実的なアドバイスも含まれています。
「研究は恋と一緒であり、何も特別なことではありません」という印象的な冒頭の一節は、研究への純粋な情熱を呼び覚ますことでしょう。
理系博士のリアルな現状と未来像
『博士になろう!理系のための研究生活ガイド B&Tブックス』には、理系研究者を目指す方に向けて、博士を取り巻く環境や博士になる方法、有能な博士になるためのヒントが書かれています。日本の博士事情と海外の違い、研究室選びの留意点など、有益な情報が満載です。
「『新たな独創的な産業技術の勃興』と『Only 1博士』の活躍する時代が到来している」という著者の見解は、これからの時代に求められる博士像を鮮明に描き出しています。
研究者こそ経済的自立を:坪田一男氏の提言
『理系のための人生設計ガイド』には、研究者の人生を多角的に捉え、特に「研究者こそ経済的自立が必要だ」という著者の強いメッセージが込められています。起業など、研究を続けるための経済力を身に付ける具体的な方法が分かりやすくまとめられています。
「『大学院を出たけどワーキング・プアだ』という筋書きは自分自身の力で変えていく」というメッセージは、研究者が自身の人生を主体的にデザインすることの重要性を強調し、勇気を与えてくれます。
研究生活を円滑に進めるための実践的アドバイス
『理系のための研究生活ガイド 第2版 テーマの選び方から留学の手続きまで』は、坪田一男氏による前著同様、理系研究者や研究者を目指す方向けに書かれています。円滑な研究生活を送るための具体的な助言が惜しみなく提供されており、学会発表や論文執筆の技術、英語学習法、読書術など、実践的なスキルアップに役立つ内容が豊富です。
「幸か不幸か、僕は何もないところからスタートした。お金はない、時間がない、設備もない。ないない尽くしの状態で、情熱だけは人一倍持っていた。」という一節は、研究への情熱が困難を乗り越える原動力となることを示唆しています。
78名の博士が語る多様なキャリアパス
『博士になったらどう生きる?78名が語るキャリアパス』では、自然科学、人文科学、社会科学といった幅広い分野の博士78名のキャリアパスが具体的に紹介されています。研究者を目指す方はもちろん、現役の研究者が自身の将来を考える上でも、多くのヒントが得られるでしょう。
「研究者は孤独になりがちですが、価値観を同じくする他者と共同し助け合うことで、よりはやくより遠くに行けるのではないかと思います」という一節は、研究者コミュニティの重要性とその可能性を伝えています。
理系女性研究者のためのキャリアとライフプラン
『理系女性の人生設計ガイド 自分を生かす仕事と生き方』は、特に理系研究者を目指す女性に向けて書かれています。大学院修了後の多様なキャリアパスや、仕事と生活のバランスの取り方について、具体的な事例と著者らの経験に基づいた助言が満載です。
「博士とは、何もない、だれもいないところで新たなものを打ち出し、その仮説を実証し、社会に賛同者を増やしていく。そのことを科学的な研究手法によってできると証明した人だ。」という言葉は、博士号が持つ本質的な価値と、それが社会に与える影響の大きさを教えてくれます。
「役に立たない研究」が持つ未来の可能性
『役に立たない研究の未来』は、基礎研究の重要性や、国の施策である「選択と集中」に関する議論、さらには「推し研究者」というユニークな概念やクラウドファンディングによる研究費調達の可能性まで、基礎研究を取り巻く現状と未来について深く掘り下げています。
「とくに博士課程に進めば、それまで誰も知らなかった事柄を突きつめて研究することができるわけですから、その後どんな職業に就こうが、その訓練が無駄になることは100パーセントない。」という一節は、基礎研究で培われる思考力や探求心が、どのようなキャリアにおいても価値を持つことを示唆しています。
猿橋賞受賞者が語る女性科学者の人生
『私の科学者ライフ 猿橋賞受賞者からのメッセージ』は、自然科学の分野で優れた業績を収めた女性科学者に贈られる猿橋賞の受賞者たちの研究内容と人生を振り返った一冊です。育児と仕事、研究の両立など、女性研究者としてのライフプランを描く上で参考になる具体的な経験が語られています。
「若いときにはわからず後になって気づくのは、人生の時間は限りがあること、それをどう生かすかは自分次第だということだ。」というメッセージは、自身の人生を能動的にデザインすることの重要性を伝えています。
アカデミアを離れて活躍する博士たちの声
『アカデミアを離れてみたら-博士、道なき道をゆく』は、理系研究者の中でも、アカデミア(大学や研究機関)を離れて民間企業やその他のフィールドで活躍している方々のリアルな声を集めた書籍です。アカデミア以外のキャリアパスを具体的に知ることができ、進路選択に悩む読者にとって貴重な情報源となるでしょう。
「本書の著者らの体験は、『アカデミアから離れることは人生が終わることだ』という固定観念、先入観、恐怖を取り払ってくれる。こうした多様な道筋を辿った方々がいるというだけでも、大きな希望になるはずだ。」という一節は、キャリアの選択肢の広がりと、新たな可能性を示唆しています。
研究者が語る「仕事と生活の両立」の舞台裏
『研究者、生活を語る 「両立」の舞台裏』は、育児や介護と研究活動を両立させている研究者たちの具体的な生活や、そこでの工夫、感情面での受け止め方などが詳細に語られています。日々の平均的なスケジュールが図示されている点も、若い読者が将来の生活をイメージする上で非常に参考になります。
「育児中の研究者が、男女を問わず周囲から十分な理解を得られ、やりたいことを諦めずに続けられる社会になっていることを祈っています。」という著者の願いは、研究者が持続可能なキャリアを築くために必要な社会的な支援の重要性を訴えかけています。
今回は、当ブログのコンテンツの中でも、研究者の皆様のライフプランニングに役立つと思われる書籍を紹介した記事についてまとめました。
何らかの参考になれば幸いです。
研究者と研究者を目指す方々が、やりたいことをあきらめないでいられることを願って。
